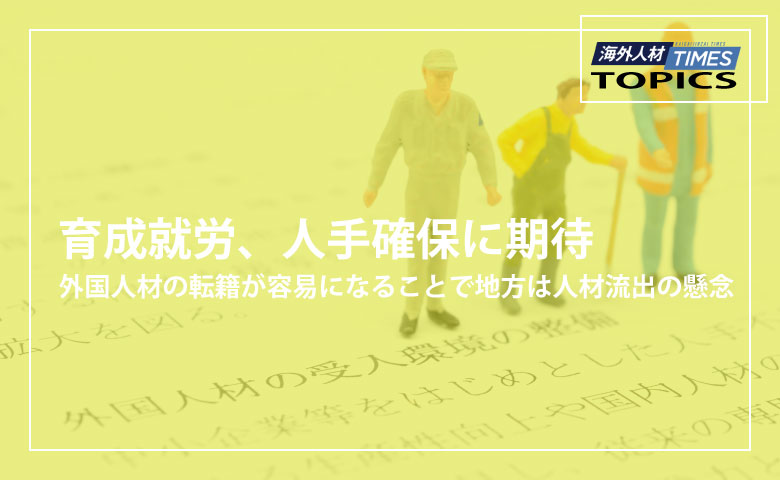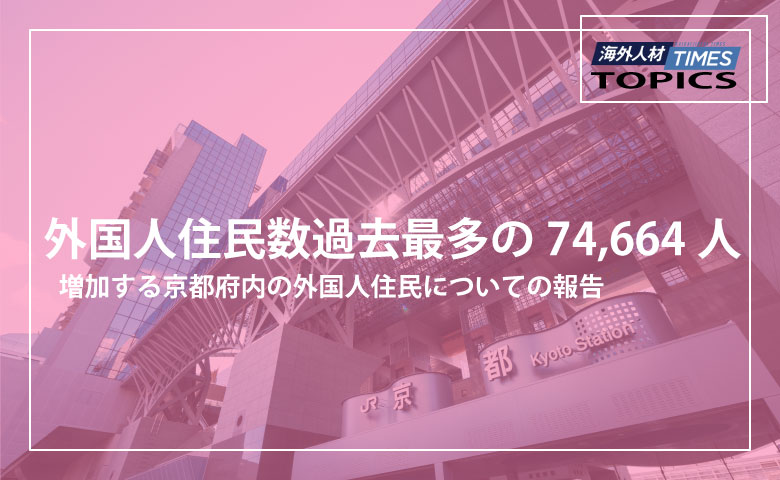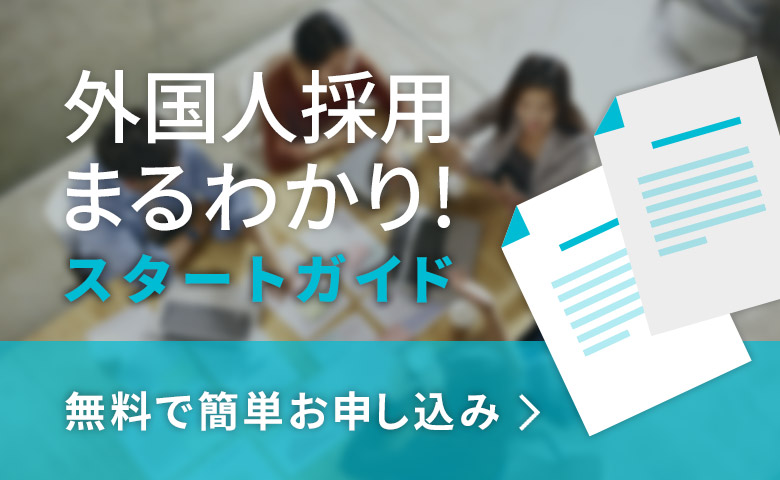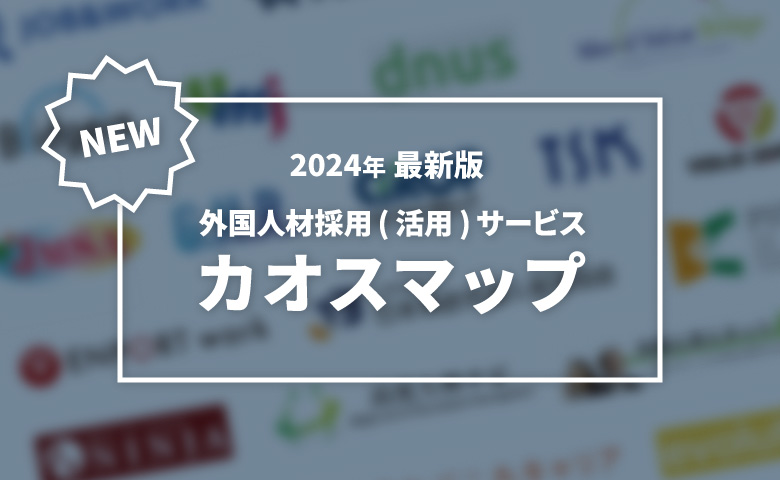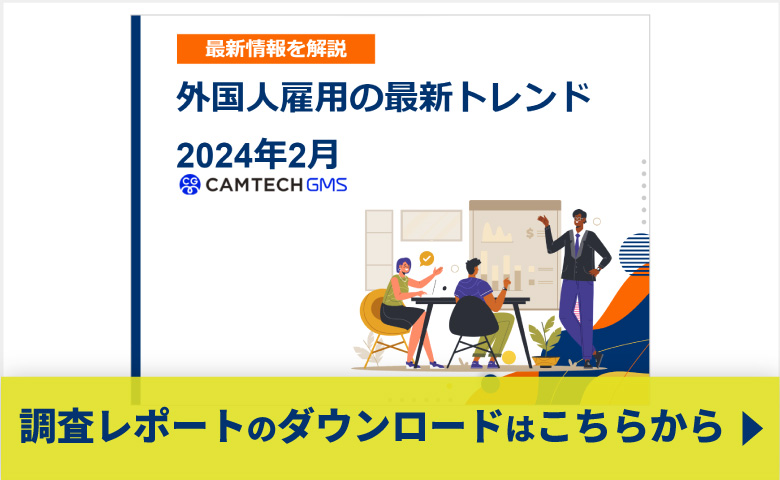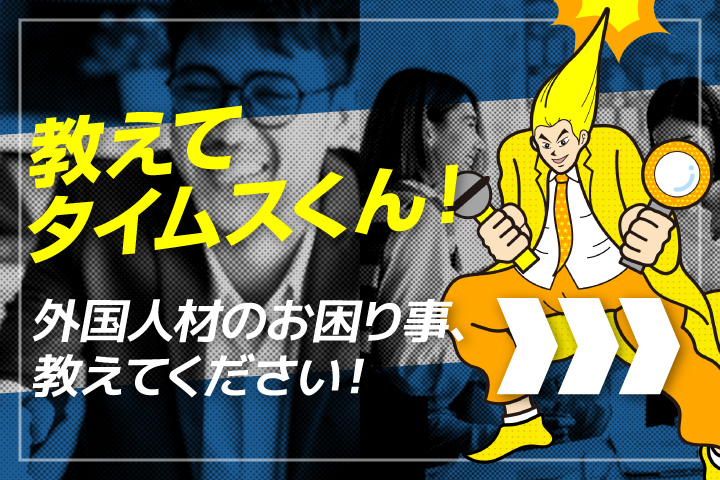契約を打ち切って外国人労働者を解雇する場合、必要な手続きや知っておくべきこと
2022.12.21

やむを得ず外国人労働者を解雇しなければならない場合、どのような流れでおこなえばよいのでしょうか?
外国人労働者の解雇は、定められたルール通りに行わなければ法律違反になることがあります。解雇に関する決まりを理解しておく必要があります。
外国人労働者の雇用中、やむを得ない事情によって解雇しなければならないこともあるでしょう。
しかし安易な解雇は遠く離れた国で働く外国人労働者にとって大変な恐怖と困難を与えてしまうものです。当然、不当な解雇は法律で認められていませんし、どうしても外国人労働者を解雇する場合は必要な手続きを踏むことが義務づけられています。
この記事では、外国人労働者を解雇する場合に必要な手続きと注意点について説明します。
CONTENTS
- 1. 日本人・外国人の解雇について
- 1-1. 解雇の種類
- 1-2. 解雇に必要な手続き
- 2. 外国人を解雇する際の注意点
- 3. 解雇で起こるトラブルと対策
- 3-1. 外国人労働者から不当解雇であると訴えられる
- 3-2. 解雇予告をせずに解雇してしまった
- 3-3. 期間の定めのある労働契約中に労働者を解雇した
- 4. まとめ
外国人労働者の解雇はどのような場合に考えられるのでしょうか?
専門家
度重なる無断欠勤や社内での迷惑行為が目に余るなど、客観的・合理的な面からみて正当な理由がある場合は解雇の対象となります。
1.日本人・外国人の解雇について
日本の企業に勤務している外国人労働者を解雇する場合は、日本の法律に基づいて解雇します。
労働者の解雇に関しては、労働契約法第16条において下記の通りに定められています。
上記の条文から考えると、従業員を解雇できるのは客観的にみて合理的な理由があり社会通念上相当である場合といえます。
言い換えるなら、正当な理由があれば労働者を解雇することに問題はありません。
具体的な事由としては、下記があげられるでしょう。
- 遅刻や無断欠勤が多い
- 協調性がなく、社内で迷惑行為を繰り返している場合
- 社内外で何らかの犯罪におよんだ場合
- 入国管理局から在留資格を取り消された場合
1-1.解雇の種類
解雇の種類としては、下記の3種類があげられます。- 普通解雇
- 整理解雇
- 懲戒解雇
普通解雇
普通解雇とは、労働者の能力不足や迷惑行為などが原因で解雇することです。労働者が業務中の失敗で上司に迷惑をかける程度では、普通解雇に至ることはほとんどありません。ただし、労働者に対して繰り返し教育しても能力の向上がみられなかったり、労働者が毎日のように迷惑行為を繰り返したりしている場合は、解雇の事由になり得ます。
そのほか、外国人労働者の在留資格が取り消された場合の解雇も普通解雇に含まれます。外国人労働者の在留資格が取り消された状態で雇用を続けてしまうと、企業側は不法就労を認めていることになり「不法就労助長罪」という罪に問われてしまうため、解雇は必要な対処といえます。なお、不法就労助長罪は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。
整理解雇
整理解雇とは、景気の悪化などでやむを得ず業務を縮小しなければならない場合、コストを抑えるために労働者を削減する解雇のことです。企業は整理解雇より前に経営を立て直すなどの努力をする必要はありますが、それでも立て直せない場合に整理解雇をするのが一般的です。
ただし、整理解雇をする際、外国人労働者ばかりを解雇すると差別的な扱いとみなされてトラブルの原因になりかねません。企業側には労働者の能力をきちんと考慮したうえでの正当な整理解雇の実施が求められます。
懲戒解雇
懲戒解雇とは最も厳しい処置であり、労働者が重大な犯罪行為、背信行為におよんだ場合などに実施されるものです。懲戒解雇をする理由としては、社内において再び同じような過ちが起きないようにすることや、厳しく対処することで社会から見た企業の信頼低下を少しでも防ぐためといったことがあげられます。
業務時間内、外、問わず、雇用している労働者が重大な罪を犯し、企業に影響がおよぶとみなされる場合は懲戒解雇をおこなうことがあります。
1-2.解雇に必要な手続き
外国人労働者を解雇する場合に必要な手続きとしては、下記があげられます。- 解雇予告をする
- 解雇理由証明書を発行する(外国人労働者から請求された場合のみ)
そのほか、必要に応じて下記の書類も提出します。
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届の提出
- 雇用保険被保険者資格喪失届の提出
- 外国人雇用状況届出書の提出
解雇予告をする
日本人、外国人を問わず普通解雇や整理解雇の場合、従業員を解雇する際は事前に解雇予告をします。解雇予告は、解雇する日の30日前までにおこなわなければなりません。なお、解雇予告をせずに解雇する場合は、労働者に対して30日分以上の解雇予告手当を支払うことで解雇とみなされます。
解雇理由証明書を発行する
外国人労働者から「解雇理由証明書を発行してほしい」と依頼を受けた場合は、解雇理由証明書を発行しなければなりません。
健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届の提出
外国人労働者が健康保険、および厚生年金保険に加入していた場合は、年金事務所に健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届のほか、外国人労働者が持っていた健康保険被保険者証を添付して提出します。
外国人労働者から健康保険被保険者証を受け取れなかった場合は、健康保険被保険者証の代わりに「健康保険被保険者証回収不能届」を提出します。
雇用保険被保険者資格喪失届の提出
外国人労働者が雇用保険に加入していた場合は、ハローワークに雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書を提出します。離職は不要であると申し出た場合は、離職証明書の提出は不要です。
外国人雇用状況届出書の提出
外国人労働者が雇用保険に加入していない場合は、ハローワークに外国人雇用状況届出書を提出します。

外国人労働者を解雇するときに起こり得るトラブルとその対策について教えてください。
専門家
トラブルの原因としては、不当解雇と訴えられることや解雇予告をせずに解雇することなどがあげられます。その対策についてはこの項目で説明します。
3.解雇で起こるトラブルと対策
外国人労働者を解雇するときに起こり得るトラブルの例としては、下記があげられます。- 外国人労働者から不当解雇であると訴えられる
- 解雇予告をせずに解雇をしてしまった
- 期間の定めのある労働契約中に労働者を解雇した
それぞれの事例について説明します。
3-1.外国人労働者から不当解雇であると訴えられる
外国人労働者から不当解雇であると訴えられると、企業側が損害賠償請求を受けることがあります。外国人労働者から不当解雇と訴えられないようにするためには、客観的・合理的な観点に基づいて解雇することが大切です。
具体的には、遅刻や無断欠勤、協調性に欠けた行動が多いなど、会社側にさまざまな迷惑をかけていることがあげられます。企業側が、外国人労働者を客観的・合理的な観点に基づいて解雇し、解雇の理由を明確に説明できれば、外国人労働者からは不当解雇だと訴えられにくくなります。
3-2.解雇予告をせずに解雇してしまった
解雇予告をせずに解雇してしまうと、トラブルの原因になりかねません。
前述した通り、解雇予告は解雇する30日前までにおこなわなければなりません。なぜなら、外国人労働者が急に解雇された場合、収入のめどが立たなくなり生活が困難になってしまうためです。また、解雇予告をおこなうことは労働基準法で定められているため、解雇予告をおこなわなければ外国人労働者から訴えられる可能性があります。
もし、解雇予告をせずに解雇せざるを得ない場合は、30日分以上の解雇予告手当を支払うことで解雇とみなされます。解雇予告をせず、しかも解雇予告手当を支払っていない場合は法律違反となり、6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられるため、注意が必要です。
3-3.期間の定めのある労働契約中に労働者を解雇した
労働契約の内容によっては、期間の定めのある労働契約が締結されることがあります。期間の定めのある労働契約に関しては、労働契約法第17条において下記の通りに定められています。
期間の定めのある労働契約を締結している場合、原則として労働者を解雇できません。解雇できるのは、労働者が会社に多大な迷惑をかけている場合など、やむを得ない事由がある場合に限られます。期間の定めのある労働契約を締結している労働者は、労働契約において期間が定められていない労働者と比べると、解雇しにくいことを理解しておきましょう。
4.まとめ
やむを得ない事情で外国人労働者を解雇しなければならない場合、客観的・合理的な理由に基づいて解雇すること、そして、通常の場合は解雇の30日前までに解雇予告が必要となります。たとえば、無断欠勤や遅刻が多かったり、協調性に欠けて頻繁に迷惑をかけていたりしている場合は解雇の理由となります。
しかし、もし解雇の理由が客観的・合理的なものでなければ、外国人労働者から訴えられる可能性があるため、正当な理由がない限り安易に解雇はできません。
解雇をする場合は、解雇の事由を確認し、法律で定められた解雇のルールに基づいておこなうようにしましょう。
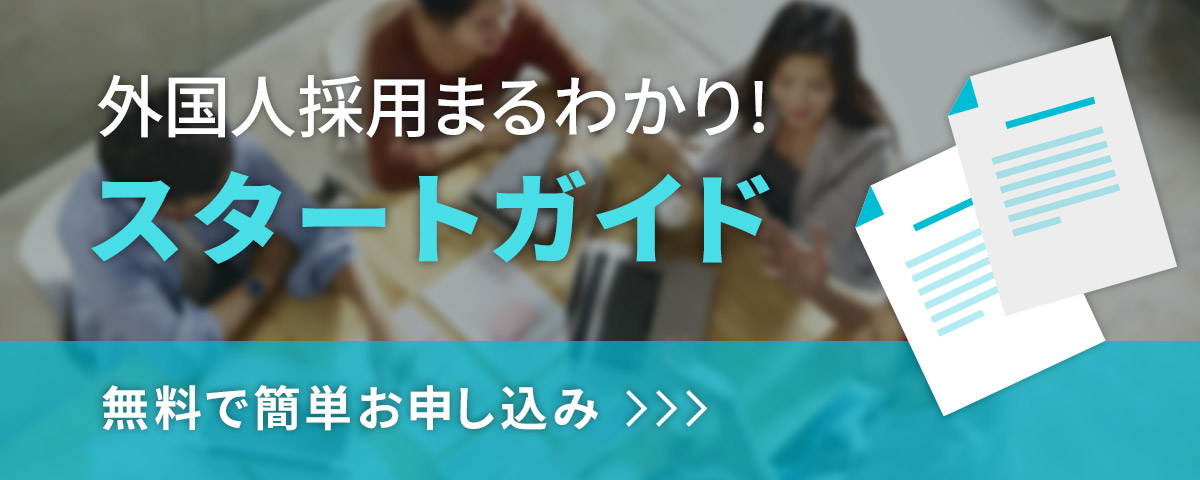
外国人採用に関するオンライン無料相談やってます!
- 雇用が初めてなのですが、私たちの業務で採用ができますか?
- 外国人雇用の際に通訳を用意する必要はありますか?
- 採用する際に私たちの業務だとどのビザになりますか?
- 外国人の採用で期待できる効果はなんですか?
上記に当てはまる企業様は、ぜひ一度ご相談ください。
関連記事
もっと見る
日本語力は気にするな! 技能実習生の「面接」で本当に大事なこと
2021.06/17
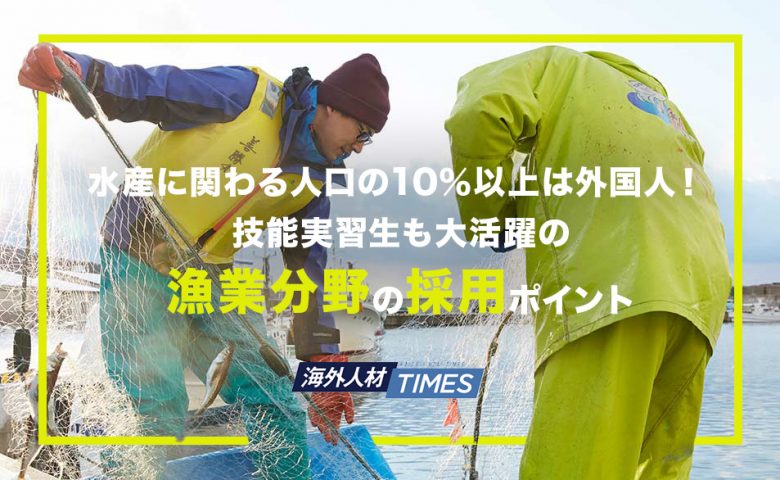
「漁業」に若い風を吹き込む技能実習生の採用の極意
2021.09/10

ホテル・宿泊業で外国人を雇用できる技人国ビザと業務範囲
2023.12/12
新着情報
もっと見る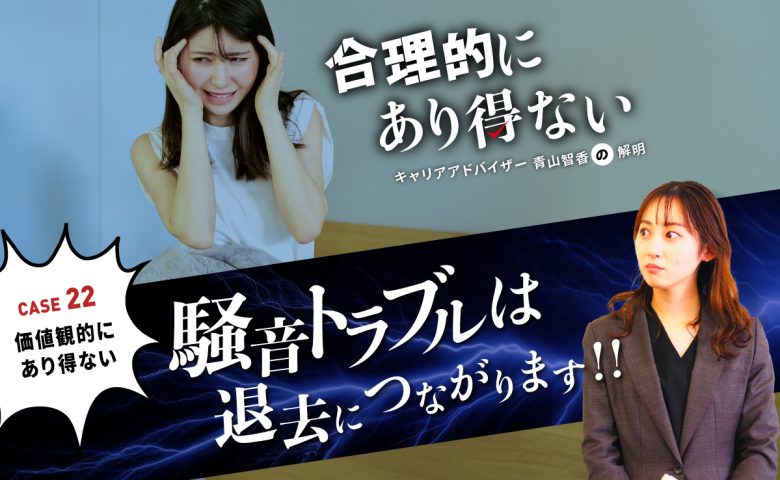
Case22 価値観にあり得ない
━騒音トラブルは退去につながります!!
2024.07/26
こんな記事が読まれています
もっと見る-
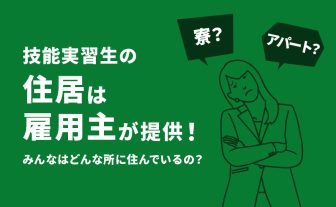
技能実習生はどこに住む? 住まいに関するルールと住居形態
在留資格「技能実習」2022.05/26
-
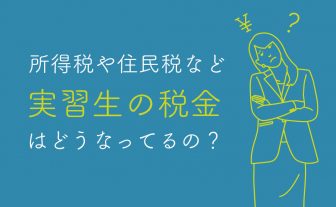
技能実習生は税金を払う?外国人の所得税と住民税をわかりやすく解説
在留資格「技能実習」2022.05/26
-

講習は何時間必要? 技能実習生の研修を来日の前後に分けて解説
在留資格「技能実習」2022.06/22
初心者向け記事
もっと見る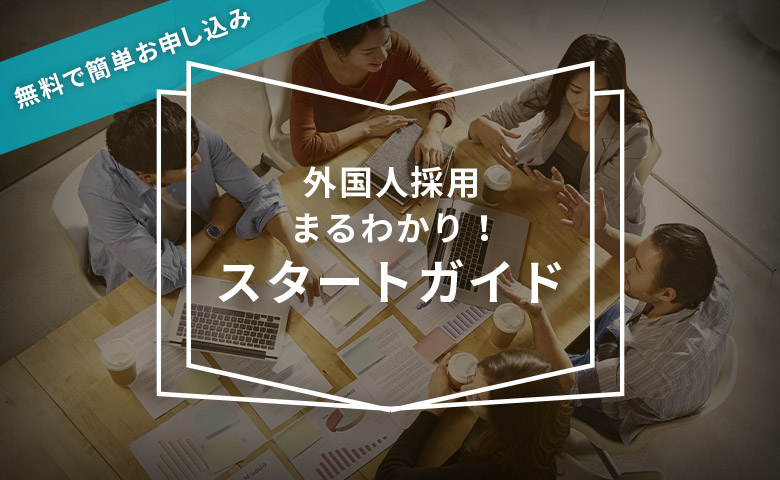
【無料DL】外国人採用を検討し始めた時に知るべき基礎が全てわかるガイドブック
2021.09/22
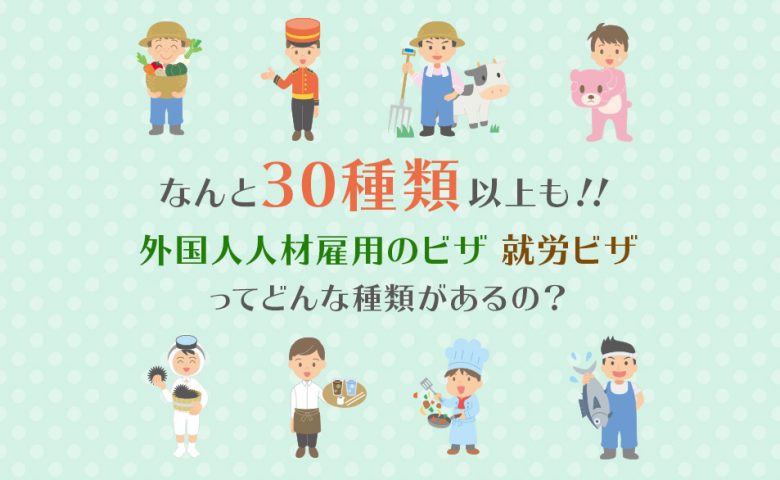
【外国人採用の基本】30種類以上ある「在留資格」とは?
2021.09/16

技能実習制度で重要な役割を担う「送り出し機関」とは?
2021.05/24
人気の記事
もっと見る-
在留資格「技能実習」
2022.05/26
-
在留資格「技能実習」
2022.05/26
-
在留資格「技能実習」
2022.06/22
おすすめキーワード