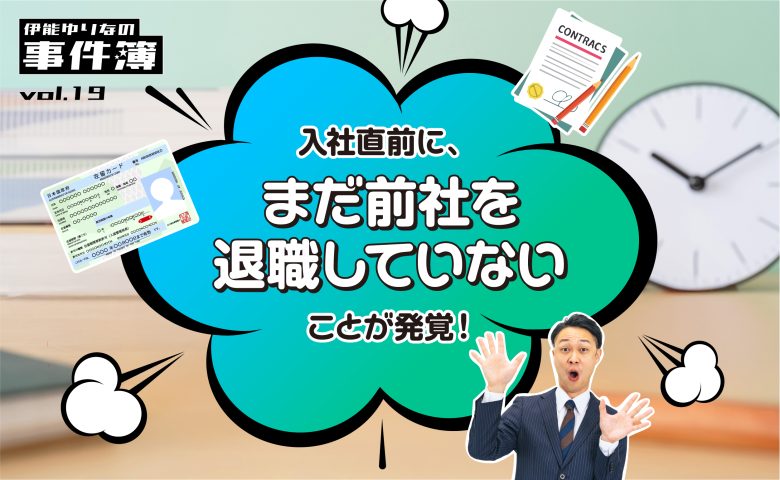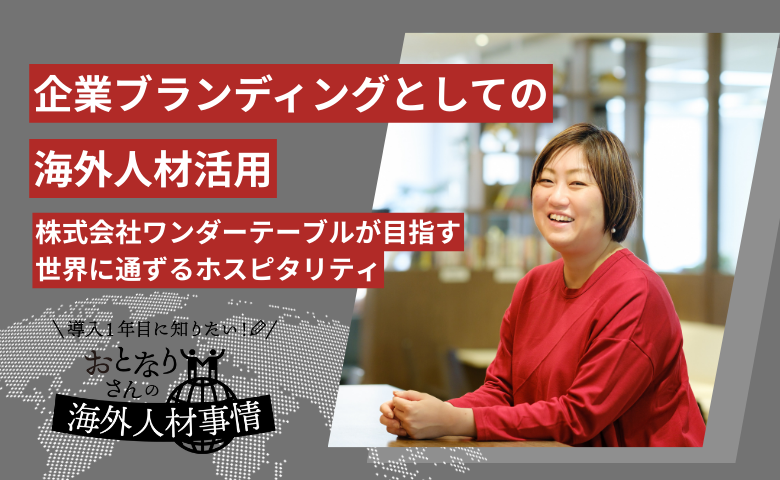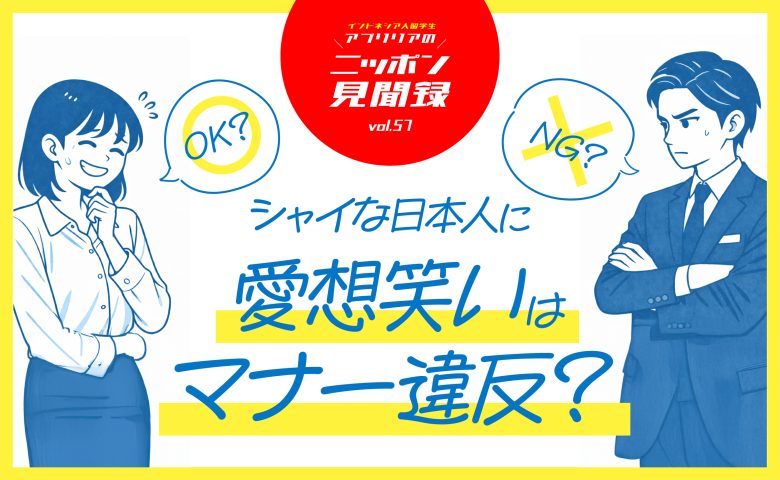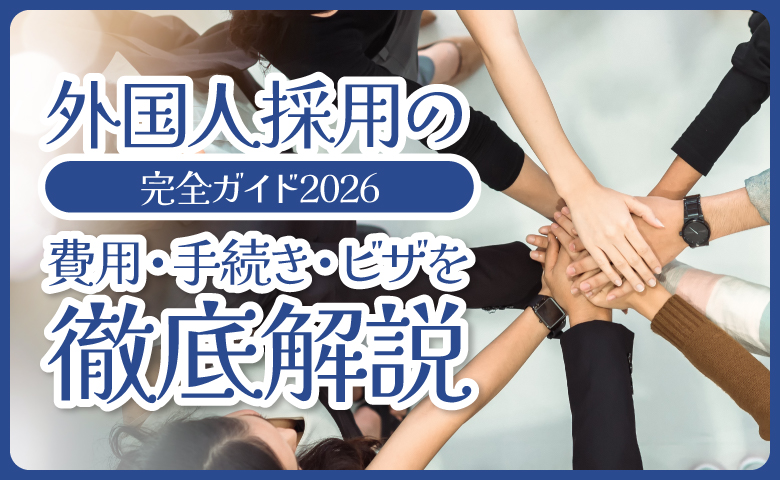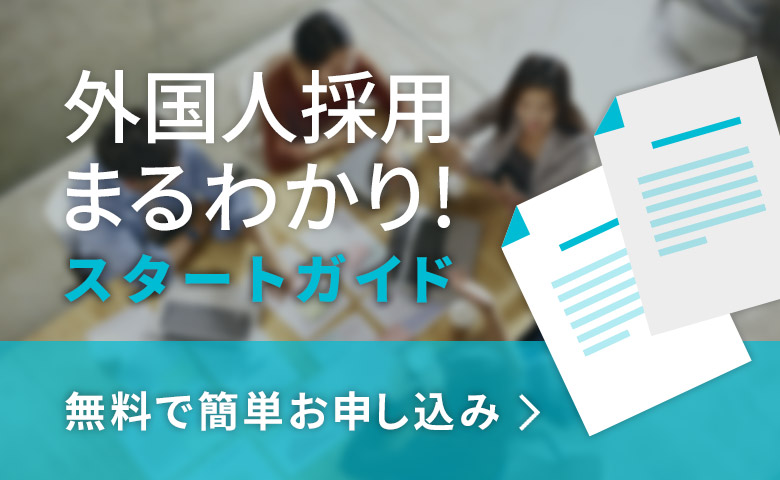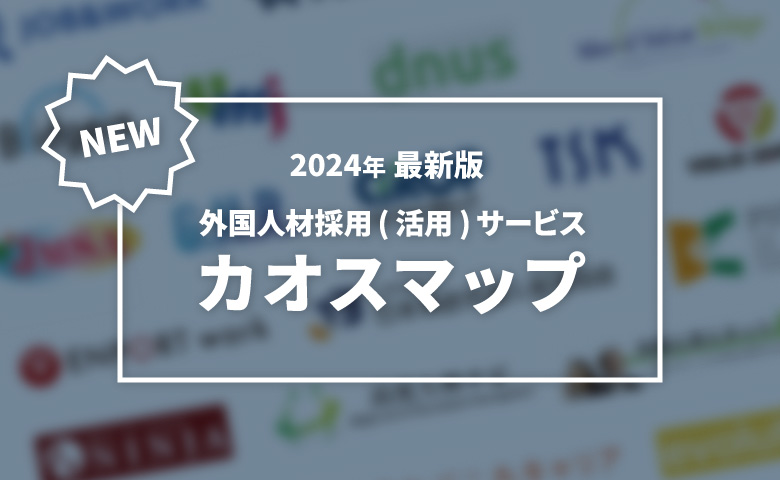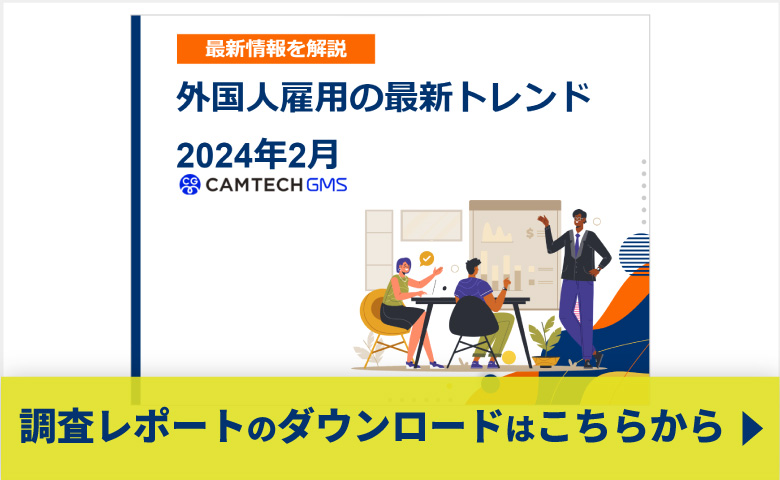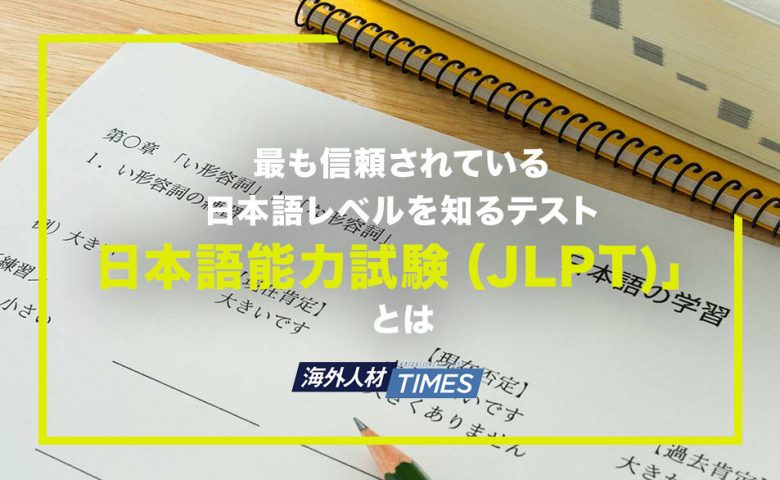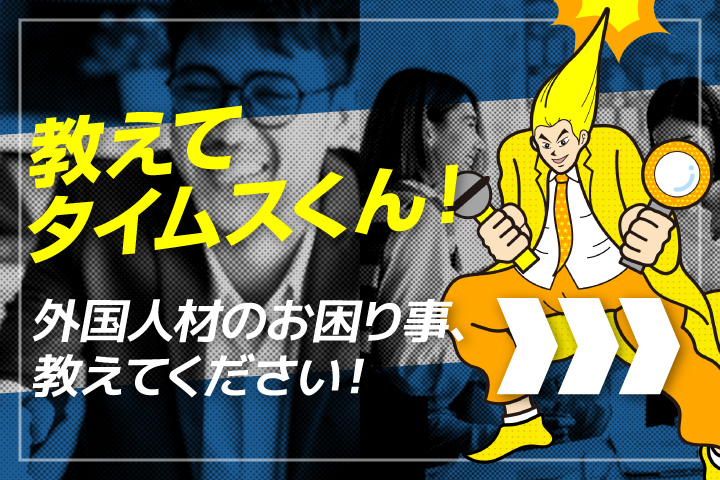外国人社員が退職するときに企業が行う手続きは?
2025.02.25
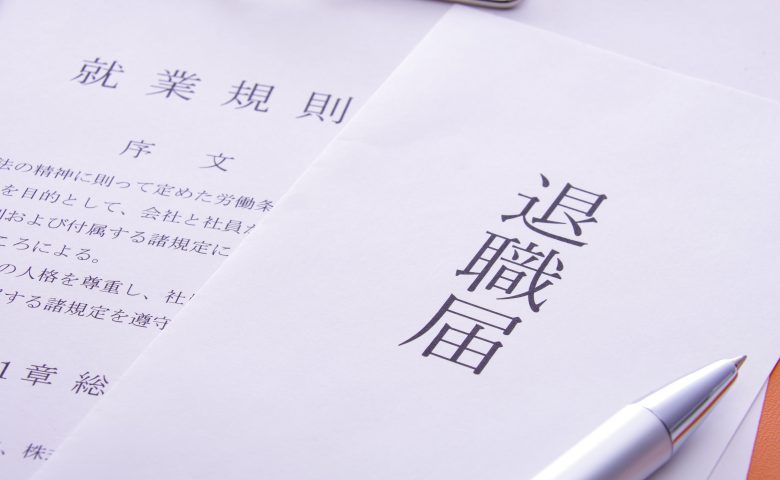
企業で外国人社員を雇用していると、場合によっては外国人社員が退職を申し出ることがあります。
退職の理由はさまざまですが、諸事情により母国に帰国しなければならないケースもあるため、退職の申し出を受けなければならないこともあるでしょう。
日本人が退職するときの手続きの流れは理解していても、外国人が退職する場合の手続きについては理解していないケースが多いのではないでしょうか。
この記事では、外国人社員が退職する場合の手続きについて、企業側が行う内容、退職する外国人が行う内容について説明します。
そのほか、外国人社員の退職手続きを行う際に注意したい内容を理解しておくと、手続きがスムーズに行えます。
CONTENTS
- 1. 外国人社員の退職時に行う手続き
- 1-1. 企業側の手続き
- 1-2. 退職する外国人社員側の手続き
- 2. 外国人雇用状況の届出
- 3. 外国人社員の退職手続きを行う際の注意点
- 3-1. 貸与品は忘れずに返却してもらう
- 3-2. 退職証明書に退職者が請求しない項目は記入しない
- 3-3. 退職後3か月で再就職や就職活動をしないと在留資格が取り消しに
- 4. 外国人社員が退職後に帰国する場合
- 4-1. 脱退一時金の手続き
- 4-2. 住民税の支払い
- 4-3. 銀行口座の解約
- 4-4. 住民票の転出届
- 4-5. その他の手続き
- 5. まとめ
1. 外国人社員の退職時に行う手続き
外国人社員の退職時に行う手続きについて、企業側が行う手続きと外国人の社員が行う手続きに分けてみていきます。
1-1. 企業側の手続き
企業側が行う手続きは、原則として日本人が退職するときとほぼ同様となりますが、それ以外に外国人が退職する場合にのみ行う手続きもあります。
その手続きの内容は下記の通りです。
- 退職証明書の交付
- 雇用保険被保険者資格喪失届の提出
- 在留カード番号の届出
それぞれの手続きについて説明します。
退職証明書の交付
退職証明書とは、会社を退職したことを証明する書類です。
日本人の退職者の場合は、社員に求められたときのみ交付すれば良いため、退職者全員に退職証明書を交付する必要はありません。
日本人が退職証明書を必要とするケースは、転職先で退職したことを証明したい場合、あるいは国民健康保険など公的な手続きを行いたいときに離職票がまだ発行されていない場合です。
しかし、外国人の退職者の場合は、在留資格の変更や更新のとき、あるいは就労資格証明書の交付を申請するときに必要となります。
そのため、外国人が会社を退職する場合は、退職証明書を必ず交付しましょう。
退職証明書には下記の内容を記載します。
- 使用期間
- 業務の種類
- その事業における地位
- 賃金
- 退職の事由
雇用保険被保険者資格喪失届の提出
雇用保険被保険者資格喪失届とは、雇用保険の給付を受ける資格を失ったことを証明する書類のことです。
外国人が退職した場合、本来は企業が入国管理局に届出をしなければなりませんが、ハローワークに雇用保険被保険者資格喪失届を提出することで、入国管理局への届出は不要となります。
雇用保険被保険者資格喪失届には「被保険者が外国人の場合のみ記入してください」という欄があり、そこには下記の内容を記入する欄があります。
- 氏名
- 在留期間
- 派遣・請負 就労区分
- 国籍・地域
- 在留資格
上記の内容を記入したうえで届出を行います。
在留カード番号の届出
2020年3月1日以降に雇用、または離職した外国人に関しては在留カード番号の届出が必要となります。
「外国人労働者在留カード番号記載様式」には下記の内容を記入して提出します。
- 事業所番号
- 事業所名
- 雇用保険の被保険者番号
- 外国人労働者の氏名
- 在留カード番号
なお、在留カード番号の届出はオンラインでも可能です。
参考:退職時に行う手続きのうち、日本人社員と同じ内容のもの
退職時に行う手続きのうち、日本人社員と同じ内容のものとしては下記があげられます。
これらの手続きも忘れずに行いましょう。
- 健康保険被保険者証の回収
- 源泉徴収票の交付
- 社会保険、労働保険の資格喪失手続き
このほか、退職後に失業手当を受け取りたい場合は、離職票も交付します。
1-2. 退職する外国人社員側の手続き
退職する外国人の社員が行う手続きとしては、下記があげられます。
- 契約機関に関する届出
- 転職先で在留資格の更新、変更
それぞれについて説明します。
契約機関に関する届出
契約機関に関する届出は、外国人が契約していた機関、つまり企業などと契約していたことを示すために行います。
「契約機関に関する届出」の書類に氏名、性別、生年月日、住所、在留カード番号、在留資格のほか、契約が終了した事由を記入します。
この届出は退職してから14日以内に提出します。
転職先で在留資格の更新、変更
必要に応じて、転職先で在留資格の更新や変更を行います。
在留資格の更新は、在留資格の有効期間が切れる前に行う必要があります。
また、在留資格は職種ごとに異なるため、現時点で保有している在留資格では再就職ができない場合があります。
再就職する場合は、その仕事に合った在留資格を調べておき、必要に応じて在留資格を変更します。
2. 外国人雇用状況の届出
外国人が退職する際は、退職日の翌月末日までに、「外国人雇用状況の届出」を管轄のハローワークへ提出する必要があります。ただし、雇用保険に加入している外国人の場合は退職時に「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出するため、外国人雇用状況の届出は省略可能です。雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限は退職日の翌日から10日以内です。
なお、外国人雇用状況の届出を行っていない場合は、受け入れを終了した日から14日以内に「中長期在留者の受入れに関する届出」を行います。雇用関係にない会社役員や研修生などが対象となるため、件数としてはあまり多くありません。
3. 外国人社員の退職手続きを行う際の注意点

外国人社員の退職手続きを行う際の注意点としては、下記があげられます。
- 貸与品は忘れずに返却してもらう
- 退職証明書に退職者が請求しない項目は記載しない
- 退職後3か月で再就職や就職活動をしないと在留資格が取り消しに
それぞれの注意点について説明します。
3-1. 貸与品は忘れずに返却してもらう
外国人社員が退職する場合、貸与品は忘れずに返却してもらいましょう。
返却してもらう主なものとしては下記があげられます。
- 社員証
- 制服または作業着
- ロッカーや住居の鍵
- その他、会社が購入した備品など
3-2. 退職証明書に退職者が請求しない項目は記入しない
退職証明書には、下記の5種類の項目を記載する必要があることについて先述しました。
- 使用期間
- 業務の種類
- その事業における地位
- 賃金
- 退職の事由
ただし、上記の項目のうち、退職者が記載を希望しない項目については記載することができません。これは労働基準法で定められています。
例えば、労働者から「退職の事由は記載しないでほしい」という要望があった場合、退職証明書に退職の事由を書くことができません。
もし、記載を希望しない項目を記載した場合、30万円の罰金が科せられます。
3-3. 退職後3か月で再就職や就職活動をしないと在留資格が取り消しに
退職する外国人が引き続き日本で仕事をする場合は、退職後3か月で再就職や就職活動をしなければ、在留資格が取り消されることを伝えておきましょう。
在留資格が取り消されてしまうと日本に滞在できなくなり、日本から出国しなければなりません。
外国人が退職するときにひとこと伝えておくと、後で外国人が困らずに済みます。
4. 外国人社員が退職後に帰国する場合
外国人であっても日本で働く以上、条件を満たす場合は、必ず社会保険に加入しなければなりません。税金の支払いも同様です。
では、外国人社員が退職後に母国へ帰国する際に、加入している公的保険などの処理はどうすればよいのでしょうか。
外国人社員が退職後に母国へ帰国する場合に必要な手続きを以下の順番に解説します。
- 脱退一時金の手続き
- 住民税の支払い
- 銀行口座の解約
- 住民票の転出届
- その他の手続き
4-1. 脱退一時金の手続き
国民年金や厚生年金は強制加入であるものの、10年以上の納付済み期間がないと老齢年金の受給資格が与えられません。そのため、老齢年金を受給する前に母国へ帰国する外国人は保険料の掛け捨てを防ぐため、支払った保険料の一部を払い戻す「脱退一時金」の制度が利用できます。将来的に再来日する予定があるなら、脱退一時金は請求せずに年金受給資格を持つ可能性を残しておいてもよいですが、再来日の予定がないなら請求しておきましょう。
4-2. 住民税の支払い
1月1日時点で日本に住所があり、一定額以上の所得を得ている人は、外国人であっても住民税を納める必要があります。通常、毎月の給与から天引きして納付しているため、退職し母国へ帰国する際には、残りの住民税を一括で支払わなければなりません。もし日本を出国するまでに支払えない場合は、出国する前に、日本に居住する人の中から自身の代わりに納税の手続きを行う納税管理人を選定し、支払いを行います。
4-3. 銀行口座の解約
帰国に際して、使わなくなった銀行口座は忘れずに解約しましょう。そのまま放置すると、思わぬトラブルに巻き込まれてしまうかもしれません。たとえば、長期間使用しないことで休眠口座に移行したり、口座情報が盗まれて詐欺に巻き込まれたりするリスクがあります。また、口座にわずかでも残高がある場合は口座維持手数料が自動的に引かれ、いずれ残高がマイナスになると、その分の支払いを請求されるケースもあります。将来的なトラブルを防止するためにも、放置するのは絶対に止めましょう。
4-4. 住民票の転出届
母国へ帰国する際は、居住地の市区町村へ住民票の転出届を提出する必要があります。住民票の居住地を元に税金や年金の請求が届くため、届け出を失念しないよう注意が必要です。 また、転出届を提出していないと、年金の脱退一時金も支給されません。「日本に住所を有していない方」という項目を満たさず、「日本に住所を有している人」として取り扱われてしまいます。
4-5. その他の手続き
ほかにも、帰国にあたっては、契約している住居、電気、ガス、水道、携帯電話、インターネットの解約など生活に関わる各種手続きが必要です。住居の解約は退去日の1~2カ月前に連絡するよう契約書に記載されている場合も多く、直前だと翌月分の家賃を請求されることもあるため注意してください。住み始めたときと同じ状態にして返すのが基本であり、部屋の状態によってはクリーニング代を請求される場合もあります。電気、ガス、水道はインターネットか電話で解約が可能ですが、立ち合いが必要になるため余裕を持って手続きすることをおすすめします。インターネットも同様のタイミングが望ましいでしょう。携帯電話の解約は直前まで使用することを考えて、帰国する1日前でも構いませんが、店舗に来店する必要があります。
5.まとめ
外国人の社員が退職するとき、企業が行う手続きは下記の3種類です。
- 退職証明書の交付
- 雇用保険被保険者資格喪失届の提出
- 在留カード番号の届出
そのほか、外国人自身で契約機関に関する届出を行う必要があります。また、必要に応じて在留資格の更新、変更の手続きも行います。
それ以外は日本人が退職する場合の手続きと同様です。
基本的な流れとしては、日本人が退職する場合と同様に退職手続きを行い、それに加えて外国人の社員が退職するときに行う手続きも合わせて行う形となります。
外国人社員の退職をスムーズに行うためにも、退職手続きは確実に実施しましょう。
外国人採用に関するオンライン無料相談やってます!
- 雇用が初めてなのですが、私たちの業務で採用ができますか?
- 外国人雇用の際に通訳を用意する必要はありますか?
- 採用する際に私たちの業務だとどのビザになりますか?
- 外国人の採用で期待できる効果はなんですか?
上記に当てはまる企業様は、ぜひ一度ご相談ください。
関連記事
もっと見る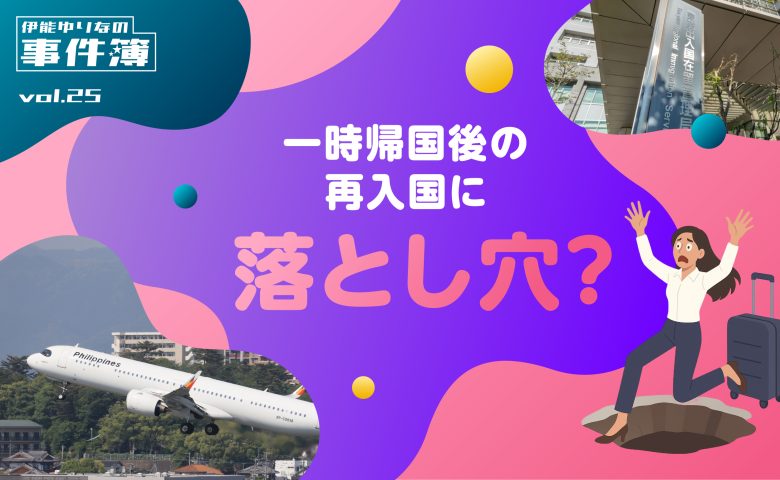
一時帰国後の再入国に落とし穴?
キャリアアドバイザー伊能ゆりなの事件簿Vol.25
2025.04/04
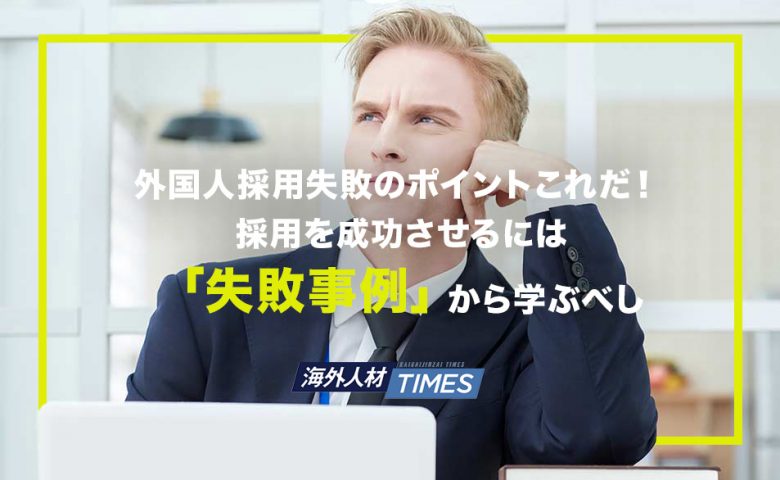
異文化コミュニケーションから考える外国人採用の極意
2021.08/26
新着情報
もっと見る
オンラインによる日本語レッスン Zipanがビジネスに強い理由とは?
2026.01/26
こんな記事が読まれています
もっと見る-
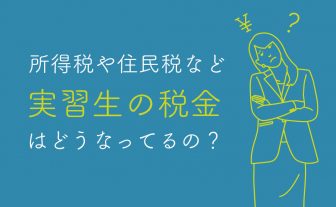
技能実習生は税金を払う?外国人の所得税と住民税をわかりやすく解説
在留資格「技能実習」2025.09/04
-
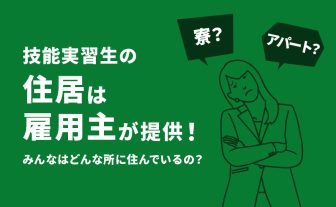
技能実習生はどこに住む? 住まいに関するルールと住居形態
在留資格「技能実習」2025.05/26
-

講習は何時間必要? 技能実習生の研修を来日の前後に分けて解説
在留資格「技能実習」2025.06/22
初心者向け記事
もっと見る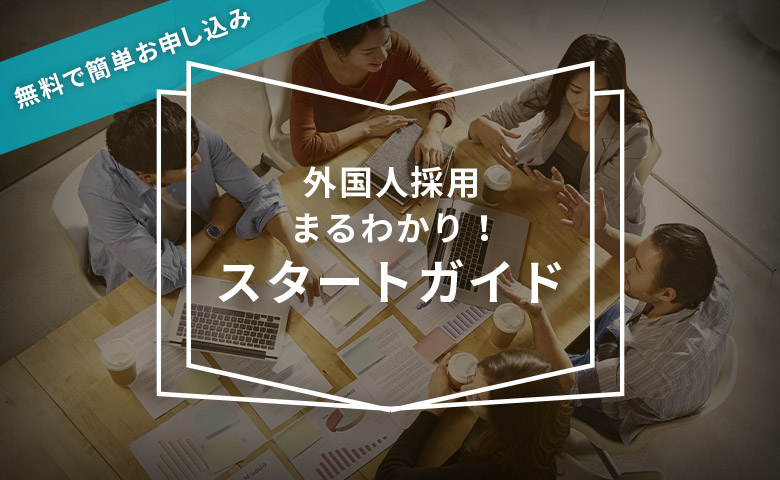
【無料DL】外国人採用を検討し始めた時に知るべき基礎が全てわかるガイドブック
2021.09/22
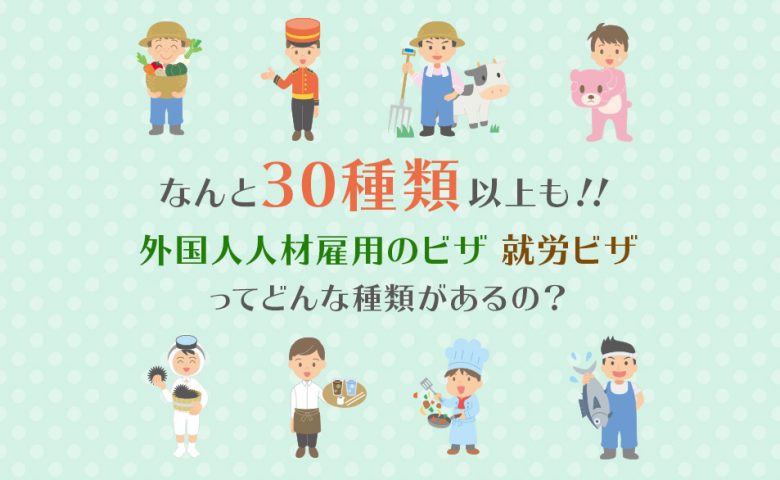
【外国人採用の基本】30種類以上ある「在留資格」とは?
2021.09/16

技能実習制度で重要な役割を担う「送り出し機関」とは?
2021.05/24
人気の記事
もっと見る-
在留資格「技能実習」
2025.09/04
-
在留資格「技能実習」
2025.05/26
-
在留資格「技能実習」
2025.06/22
おすすめキーワード
関連記事
2021.08/26